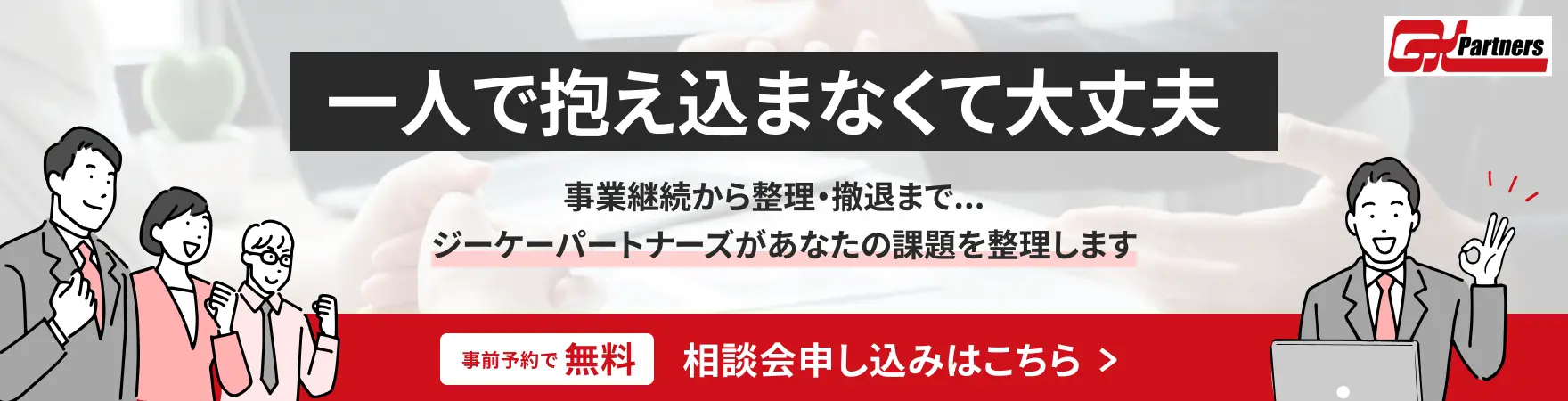企業経営において不良債権の処理を検討する際、「債権放棄と債務免除の違いがよく分からない」と感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。
一般的に、債権放棄と債務免除は法的には同じ効果を持ち、表現の違いにすぎません。
ただし、実務上は立場によって意味合いが異なります。
つまり、同じ出来事を債権者側から見るか、債務者側から見るかの違いですが、実務においては手続き方法や税務処理が異なるため注意が必要です。
本記事では、
・債権放棄と債務免除の基本的な考え方
・実際の手続きの流れ
・税務上の注意点と債務超過企業が押さえるべきポイント
について分かりやすく解説します。
適切な債権処理を行うことで、資金繰り改善や債務超過解消につなげることが可能です。
ぜひ参考にしてください。
債務超過企業のM&Aや企業再生に関するご相談は、ジーケーパートナーズにお任せください。
私的整理ガイドラインを活用した事業譲渡や、債権放棄を含む再生スキームなど、一般的なM&A仲介会社では取り扱いが難しい案件にも数多く対応してきた実績があります。
「資金繰りが限界に近い」「債務超過でM&Aが難しいと言われた」
そのようなお悩みをお持ちの経営者様も、ぜひ一度ご相談ください。
債権放棄と債務免除の違い
債権放棄と債務免除は、基本的には同一の法律行為を異なる立場から表現したもので、いずれも債務を消滅させる効果を持ちます。
以下のようにどちらの立場から見るかによって呼び方が以下の通り変わります。
| 視点 | 用語 | 意味 |
| 債権者の視点 | 債権放棄 | 自分が持つ債権を放棄する行為 |
| 債務者の視点 | 債務免除 | 債務の返済義務を免除してもらう行為 |
どちらも債権者による単独行為であり、債権者の意思によって債務を消滅させられる点は共通しています。
法的効力や基本的な手続きの流れは同じですが、実務上は債権者側と債務者側で必要となる社内手続きや税務上の取り扱いに差が生じる場合があるため、注意が必要です。
債権放棄とは(債権者の視点)
債権放棄とは、債権者が自らの債権を放棄し、返済を求めないことを意思表示する行為です。
たとえば、A社がB社に1000万円を貸している場合、A社が「この1000万円は返済不要とします」と表明すれば、それが債権放棄にあたります。
債権者にとっては貸付金を回収できなくなる一方で、税務上の要件を満たせば貸倒損失として損金算入できるというメリットがあります。
ただし、次のような場合には注意が必要です。
- 経済合理性が認められない債権放棄
→単に取引先を救済する目的で行った場合は「寄附金」とみなされ、損金算入に制限がかかる。
- 債務者の再建可能性が不透明なケース
→債務者の事業再生につながらないと判断されれば、税務上認められない可能性がある。
つまり、債権放棄は単なる「免除」ではなく、債務者の再建や取引維持といった合理性が求められる行為です。
実務で検討する際には、必ず専門家の確認を得ながら進めることが重要です。
債務免除とは(債務者の視点)
債務免除とは、債務者が債権者から借入金の返済義務を免除してもらう行為です。
前述の例でいえば、B社が「A社から1,000万円の借金を免除してもらった」という状況が債務免除にあたります。
債務者にとっては、負債が減少して財務体質が改善するメリットがあります。
一方で、免除を受けた金額は「債務免除益」として益金に算入され、法人税の課税対象となる可能性があります。
ただし、以下のようなケースでは課税が軽減または回避できることがあります。
- 繰越欠損金がある場合:免除益と相殺することで課税されないことが多い
- 資本金等の額を限度とする免除:一定の範囲内であれば課税対象外となる
- 会社更生法・民事再生法等の法的整理に基づく免除:課税が限定的になる場合がある
つまり、債務免除は財務改善効果が大きい一方、税務処理を誤ると予期せぬ課税負担が生じるリスクもあるため、専門家の確認が不可欠です。
債権放棄と債務免除の実務手続の違い
債権放棄と債務免除は、法的には同じ行為ですが、実務においては債権者側と債務者側で求められる対応が異なります。
債権放棄はあくまで債権者が主体となる単独行為ですが、債務者側にとっては「債務免除益」として課税対象になり得るなど、双方に異なる影響が生じる点に注意が必要です。
そのため、実務で対応する際には以下の観点が重要となります。
- 税務上の取り扱い:債権者側では損金算入要件、債務者側では債務免除益課税の有無
- 証拠保全の徹底:契約書・覚書・議事録などを残し、後日のトラブルや税務調査に備える
- 合理性の確保:債務者の再建可能性や取引継続の必要性が説明できること
つまり、債権放棄と債務免除は単なる「表現の違い」ではなく、実務上は手続きや税務処理の観点から正しい対応が不可欠です。
以下で、それぞれの立場からの具体的な手続きや注意点を詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
債権者側の手続き
債権者側が債権放棄を行う場合、次のような手続きが必要です。
- 支払い催促の実施
→まずは督促を行い、債務者が本当に返済困難な状況かを確認する
- 債務者の経営・財務状況の調査
→決算書・資金繰り表などを精査し、放棄に経済合理性があるかを判断する
- 債権放棄通知書の作成と送付
→内容証明郵便(配達証明付き)で送付することが必須
この通知により、債権者の一方的な意思表示で債権は消滅し、債務者の同意は不要となる
- 証拠保全と保管
→通知書は税務申告にも必要となるため、同一内容を3通作成し「債権者控え」「債務者控え」「郵便局控え」として保管する
さらに、債権放棄の実行にあたっては、債権者側で取締役会決議など社内承認手続きを経ておくことが望ましく、税務調査においても合理性の根拠として有効です。
債務者の対応
債務者側は、債権者からの債権放棄通知を受け取る受動的な立場にあります。
通知書が到達した時点で債務は自動的に消滅するため、特別な承諾や手続きは不要です。
ただし、受け取った通知書は税務処理における「債務免除益」計上の根拠資料となるため、必ず適切に保管しておきましょう。
また、債務免除益は法人税法上の益金に算入されるため、課税対象となる可能性があります。
ただし、以下のようなケースでは課税が軽減または回避される場合があります。
- 繰越欠損金がある場合:免除益と相殺して課税されないことが多い
- 再生・更生などの法的整理に基づく免除:特例により課税が制限されるケースがある
したがって、債務免除は財務改善に有効な手段である一方、税務面で思わぬ負担が生じるリスクもあります。
実務上は、必ず税理士などの専門家に相談し、最適な処理方法を検討することをおすすめします。
必要書類と通知方法
債権放棄・債務免除において最も重要な書類が「債権放棄通知書」です。
この通知書には、以下の内容を必ず明記する必要があります。
- 免除する債権の詳細(具体的な金額、契約の内容、発生時期)
- 債務免除を行う理由(債務者の再建可能性や取引継続の必要性など、経済合理性が分かる記載が望ましい)
- 債権者の署名または記名押印
送付方法は、配達証明付き内容証明郵便が必須であり、普通郵便では税務上認められません。
確実な証拠保全のため、同一文面を3通作成し、債権者・債務者・郵便局でそれぞれ保管します。
さらに、債権者側では取締役会決議や社内稟議書などの承認手続きを整えておくことで、税務調査時に「経済合理性を持った債権放棄」として説明しやすくなります。
これらの書類は税務調査時の重要な証拠書類となるため、長期間にわたって適切に保管することが不可欠です。
税務上の取り扱いと注意点
債権放棄と債務免除は法的には同じ行為ですが、税務上の取り扱いは債権者側と債務者側で大きく異なります。
適切な税務処理を怠ると、予期せぬ税負担や税務リスクが生じる可能性があるため、事前の検討が不可欠です。
- 債権者側の処理
→債権放棄した金額は原則として「貸倒損失」として損金算入可能
ただし、経済合理性が認められない場合は「寄附金」とみなされ、損金算入に制限がかかる
- 債務者側の処理
→免除された金額は「債務免除益」として益金算入され、法人税の課税対象となる可能性がある
ただし、繰越欠損金との相殺や法的整理に基づく場合など、課税が軽減・回避されるケースもある
このように、同じ「債務免除」であっても、立場によって税務処理が異なるため、必ず専門家の助言を受けながら対応することが重要です。
債権放棄の税務処理
法人が債権を放棄した場合、その金額を「貸倒損失」として損金算入できる可能性があります。
ただし、税務上は経済合理性の有無が厳しく問われ、要件を満たさなければ損金算入が認められません。
貸倒損失として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 債務者が弁済不能であること(破産・清算・経営再建困難など)
- 債権回収のための適切な手続きが行われていること(督促、調査、金融機関との協議など)
- 書面による債権放棄が実行されていること(内容証明郵便などで証拠保全されている)
また、親子会社間の債権放棄については注意が必要です。
完全支配関係がある場合には、原則として寄附金扱いとなり損金不算入となる特殊ルールが適用されます。
つまり、債権放棄を損金算入できるかどうかは、形式だけでなく合理性・手続き・関係性によって大きく左右されるため、必ず専門家の確認を得ることが重要です。
債務免除の税務処理
債務免除を受けた法人は、免除された金額を「債務免除益」として益金算入しなければなりません。
この債務免除益は法人税の課税対象となります。
ただし、多くの債務超過企業は繰越欠損金を抱えているため、免除益と相殺することで課税が発生しないケースもあります。
一方で、債務免除益が繰越欠損金を上回った場合には、その超過分に法人税が課税される点に注意が必要です。
また、親子会社間の債務免除では、完全支配関係(100%子会社など)がある場合には原則として益金不算入とされ、課税対象から除外されます。
つまり、債務免除は財務体質の改善に有効な手段ですが、税務上の取扱いはケースによって大きく異なるため、必ず事前に専門家へ確認することが重要です。
債務超過については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。
関連記事|債務超過になるとどうなる?倒産・株価の影響も徹底解説
実際の活用場面
債権放棄と債務免除は、企業経営の実務においてさまざまな場面で活用されています。
特に中小企業では、経営者と会社の関係が密接であるため、多様な活用パターンが見られます。
企業の事業再生・経営改善
業績悪化により債務超過に陥った企業の財務健全化において、債権放棄(債務免除)は有効な手段のひとつです。
たとえば、10億円の負債を抱える企業が8億円の債務免除を受ければ、負債を2億円まで圧縮し、再建のための体制を整えることが可能となります。
この場合、企業側には債務免除益8億円が発生します。
過去の繰越欠損金と相殺できる場合には課税が生じないケースもありますが、繰越欠損金を上回る部分については法人税が課税されるため注意が必要です。
一方、金融機関や債権者側にとっても、回収が困難な債権を整理し「貸倒損失」として損金算入することで、自社の財務健全性を維持する効果があります。
ただし、債権放棄・債務免除が税務上認められるためには、経済合理性の証明や適切な手続き(内容証明での通知、社内承認、証拠保全など)が欠かせません。
したがって、実務においては必ず専門家の助言を得ながら進めることが重要です。
親子会社・グループ企業間の債権整理
親会社が子会社の経営支援を目的として債権放棄を行うケースもあります。
たとえば、グループ全体の事業戦略として不採算事業から撤退する場合や、事業統合を行う際に親子会社間の債権債務を整理する手段として用いられます。
特に完全支配関係(親会社が子会社株式を100%保有)にある場合には、税務上特別な取扱いが適用される点が特徴です。
- 債権者側(親会社):債権放棄損失は原則として損金不算入
- 債務者側(子会社):債務免除益は原則として益金不算入
このため、親子間での債権放棄・債務免除は、グループ全体での税負担に影響を与えず、財務体質の改善を純粋に進めることが可能です。
ただし、この取扱いが適用されるには完全支配関係の有無や合理的な事業目的の存在が前提となるため、実行にあたっては事前に税務専門家の確認を受けることが不可欠です。
役員借入金の整理・相続対策
経営者個人が会社へ貸し付けている貸付金を整理する場面でも、債権放棄を活用することが可能です。
中小企業では、経営者が資金繰りのために個人資金を会社に貸し付けているケースが少なくありません。これらの債権を放棄することで、次のようなメリットがあります。
- 会社側のメリット
→負債が減少し、貸借対照表が改善されることで財務体質が強化される
- 経営者個人のメリット
→将来回収の見込みが薄い債権を生前に整理でき、相続財産を減らすことで相続税負担を軽減できる可能性がある
債務免除により会社側では債務免除益が発生し、法人税の課税対象となる可能性があります。
そのため、実行前に繰越欠損金の残高を確認し、免除益と相殺して課税負担を抑えられるかどうかを検討することが重要です。
M&A・企業買収時の債権整理
企業買収やM&Aのプロセスにおいては、対象企業の財務体質を改善する目的で債権放棄が行われる場合があります。
たとえば、買収前に金融機関や親会社などの債権者が一部の債権を放棄することで、対象企業の純資産を改善し、買収価格の調整や買収後の事業運営を円滑に進めやすくなるのです。
このような債権放棄は、債権者にとっては戦略的な判断となります。
短期的には損失を受け入れることになりますが、以下のようなメリットを期待できるケースがあります。
- 買収企業との長期的な取引関係の維持
- グループ全体の再編による効率化
- 新たなビジネスチャンスや市場機会の獲得
ただし、すべてのM&Aで債権放棄が行われるわけではなく、経済合理性と再建可能性が前提です。
そのため、実務上は金融機関・債権者・買収企業の三者で十分な協議を行い、税務上の取扱いや将来の事業計画を踏まえたうえで進める必要があります。
ジーケーパートナーズは、中小企業活性化協議会の外部専門家として、私的整理ガイドラインを活用した事業譲渡や特別清算を含む企業再生支援を数多く手がけてきました。
一般的なM&A仲介会社では対応が難しい債務超過企業のM&Aや再生スキームにも豊富な実績があります。
「資金繰りが限界に近い」「金融機関や取引先との調整が不安」——
そんなお悩みをお持ちの経営者様も、どうぞご安心ください。
まずは無料個別相談会で、貴社に最適な解決策を一緒に検討いたします。
債権放棄や財務改善を伴うM&Aについて詳しく知りたい方は、債務超過企業の場合の実際の進め方や注意点を解説した下記の記事も参考になります。
関連記事|債務超過企業でもM&Aは可能!成功のための5つのステップ
私的整理・法的整理での活用1
企業の債務整理において、債権放棄は重要な役割を担います。
(1)私的整理
- 金融機関などの債権者が自主的に債権の一部を放棄することで、企業の資金繰り改善や事業継続を支援する方法です
- 裁判所を通さず合意形成で進められるため、柔軟でスピード感のある対応が可能ですが、全債権者の同意が必要というハードルもあります
- 裁判所の関与のもとで手続きが進められ、強制的に債権放棄が実行される仕組みです
- 債権者の一部が反対しても裁判所の認可によって再建計画を実行できるため、大規模案件や利害関係者が多数いるケースで利用されます
いずれの手続きも、「事業の継続価値>清算価値」と判断される場合に、債権放棄を含む事業再生スキームが選択されるのが一般的です。
一方で、再建可能性が低いと判断されれば、清算手続きが選択されることもあるため、早期に専門家へ相談し、最適な再生スキームを検討することが不可欠です。
まとめ
債権放棄と債務免除は、法的には同じ効果を持つ手続きであり、立場の違いによって呼び方が変わるだけです。
- 債権者の立場から見れば「債権放棄」
- 債務者の立場から見れば「債務免除」
いずれも債権者の一方的な意思表示によって債務が消滅する単独行為であり、企業の再生や財務改善において重要な役割を果たします。
実務においては、次のような場面で戦略的に活用されます。
- 企業再生:資金繰り改善や債務超過解消を目的とした債権調整
- 親子会社間の債権整理:グループ再編や不採算事業からの撤退に伴う処理
- 役員借入金の相続対策:経営者個人の貸付金を整理し、相続財産を圧縮
- M&A時の財務改善:買収前に債務を圧縮し、純資産を改善
ただし、税務リスクや手続きの複雑さが伴うため、安易に実行することは危険です。
債権放棄・債務免除を検討する際は、必ず税理士や弁護士など専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。
債権放棄や債務免除を含む企業再生・M&Aでお困りの際は、ジーケーパートナーズにご相談ください。
当社は企業再生の専門家として、私的整理ガイドラインを活用した事業譲渡や特別清算、再生スキームを絡めたM&A支援、債務超過案件の取り扱いなどに豊富な実績を有しています。
「金融機関との交渉が不安」「債務超過でM&Aが難しいと言われた」
そのようなお悩みを抱える経営者様も、どうぞご安心ください。
まずは無料個別相談会にて、貴社の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。