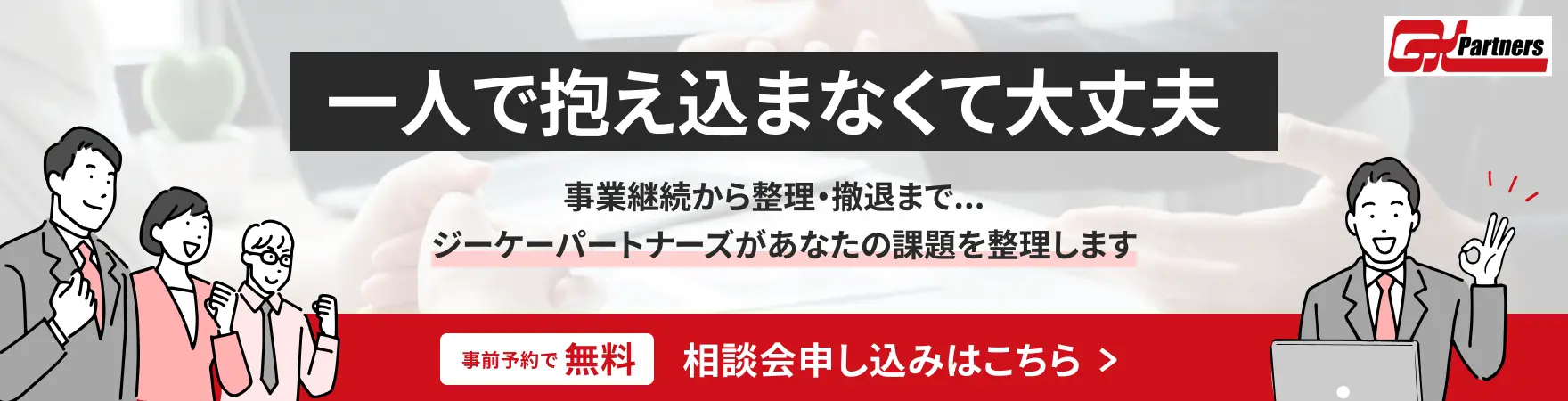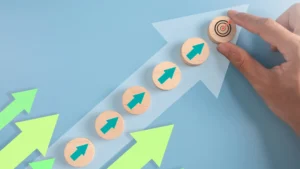
「多額の借入金があるため、自分の代で廃業するしかない」と考えてしまう経営者の方は少なくありません。
しかし、債務超過の状態であっても「債務免除」を受けることで、事業承継を実現できる可能性があります。
本記事では、
- 債務超過企業における事業承継の課題
- 債務免除の仕組みと活用方法
- 事業を引き継ぐための具体的なポイント
について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
債務超過の企業では、後継者や買い手にとって「債務の引継ぎ」が最大の障害になります。
そのため、一般的なM&A仲介会社では債務超過案件を取り扱わないことも多く、承継の選択肢が限られてしまいます。
しかし、再生スキームを組み合わせることで、「負債の処理」と「事業の承継」を両立させる可能性が生まれます。
近年は「私的整理ガイドライン」を活用し、
- 事業譲渡や会社分割によって事業を新会社へ移転
- 旧会社は特別清算を行い、債務を免除
といった手法が増えています。
これが実現できれば、後継者や買い手が債務を背負わずに事業を引き継げる可能性が生まれ、会社の未来を繋ぐ選択肢となります。
債務超過での事業承継は、法務・税務・金融機関調整など複雑な知識と経験が求められます。
「何から手をつければよいか分からない」とお悩みの経営者様は、まず専門家にご相談ください。
- 中小企業活性化協議会の外部専門家として多数の再生支援に関与
- 債務超過案件に強いM&A仲介支援を提供
しており、貴社の状況に合わせた最適なスキームをご提案できます。
現在、無料個別相談会を実施しています。
貴社の現状に合わせた最初の一歩を具体的にご提案します。
債務超過とは何か詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
関連記事|債務超過とは?原因と解決策を解説|債務超過の解決策も紹介
- 債務超過企業でも債務免除をすれば事業承継が可能
- 金融機関はなぜ債務免除に応じるのか
- 破産による回収不能を避けるため
- 事業の将来性や社会的価値を評価するため
- 債務超過企業が事業承継を実現するための3つのポイント
- ポイント1:第二会社方式で優良事業を切り出す
- ポイント2:旧会社を特別清算し債務を整理する
- ポイント3:繰越欠損金で債務免除益の税金を回避する
- 事業承継における経営者保証の整理
- 会社と経営者の債務整理に使える主な制度
- 原則として経営者の保証債務も整理の対象になる
- 債務免除を活用した事業承継の注意点
- 後継者や従業員への丁寧な説明と合意が求められる
- 許認可の再取得や取引契約の再締結が必要になる
- 専門家選びで成否がわかれる
- まとめ
債務超過企業でも債務免除をすれば事業承継が可能
事業承継において最大の壁となるのが、過大な借入金や債務超過の状態です。
後継者にとって、債務まで引き継ぐことは大きな負担となり、承継を断念せざるを得ないケースも少なくありません。
そこで検討すべき可能性のある選択肢の一つが、「債務免除」という手続きです。
債務免除とは、債権者(金融機関など)の同意を得て、会社の債務の全部または一部を免除してもらう仕組みを指します。
この制度が活用できれば、
- 後継者が過大な借入金や個人保証のプレッシャーから解放される
- 財務内容を健全化した状態で事業を引き継げる
- 債務超過でも廃業を回避し、事業存続の道を確保できる
といった大きなメリットがあります。
ただし、債務免除を伴う事業承継は、
- 債権者(金融機関)との調整
- 法務・税務の知識
- M&Aや私的整理のスキーム設計
といった高度で専門的なノウハウを要します。
そのため、専門家の支援を受けることで、承継後の安定経営につながる「最適な解決策」を選択できる可能性が高まります。
M&A支援機関を利用するメリットは、以下の記事で解説しておりますのであわせて参考にしてください。
関連記事|M&A支援機関とは?M&A支援機関を利用するメリットをご紹介
金融機関はなぜ債務免除に応じるのか
「債務免除」と聞くと、金融機関が損をしてまで会社を助けているように思われる方も多いかもしれません。
しかし、金融機関が債務免除に応じる背景には、経済的な合理性が見込まれる場合に限られることが多いです。
金融機関にとって、企業が破産・倒産してしまうと、
- 債権の大半が回収不能になる
- 担保を処分しても回収額は限定的
- 取引関係の断絶による経済的損失
といった大きなリスクが生じます。
一方で、事業再生を前提に一部の債務を免除することで、企業が存続し、一定の債権を回収できる可能性が高まります。
つまり、金融機関が債務免除に応じるのは「損をしている」のではなく、より大きな損失を避け、長期的に合理的な回収が見込めると判断する場合があるためです。
この金融機関の考え方を理解することで、経営者は次のようなポイントを押さえる必要があります。
- 債務免除は「特別な救済」ではなく、経済合理性に基づく調整手段である
- 金融機関と協調しながら事業再生スキームを構築することが重要
- 専門家を介することで、金融機関との交渉を有利に進められる可能性がある
金融機関が債務免除に応じるのは、決して情けや特別待遇ではなく、「破産よりも再生の方が合理的」という冷静な判断に基づくものです。
その仕組みを理解することが、経営者にとって事業承継・再生の可能性を広げる第一歩となります。
破産による回収不能を避けるため
金融機関が債務免除に応じるかどうかを判断する際の基準は、「清算した場合の回収額(清算配当)」と「再生を支援した場合の回収額」を比較して、どちらが合理的か、という点にあります。
もし企業が事業承継を断念し、破産・清算の道を選んだ場合、
- 会社資産の多くはすでに担保として差し押さえられている
- 担保権のある一部金融機関しか優先的に回収できない
- 一般の金融機関が回収できる金額はごくわずかにとどまる
といった状況が多く見られます。
一方で、債務の一部を免除してでも優良事業を存続させ、事業承継や再生を図った方が、将来的な返済原資を確保できる可能性があります。
その結果、金融機関にとっても最終的な回収総額が大きくなることが期待できるのです。
経営者としては、金融機関に対して以下の点を理解し、伝えることが重要です。
- 「清算より再生の方が合理的である」ことを示す資料や計画を提示する
- 再生後の収益見込みや返済可能性を具体的に説明できる事業計画を用意する
- 金融機関の立場を理解し、交渉の場を「協力関係」に変える視点を持つ
これにより、金融機関との交渉は単なるお願いベースではなく、経済合理性に基づく提案となり、債務免除に応じてもらえる可能性が生まれます。
金融機関が債務免除に応じる理由は、感情的な「支援」ではなく、「清算よりも再生の方が合理的である」という判断基準にあります。
事業の将来性や社会的価値を評価するため
金融機関が再生支援や債務免除を検討する際、注目するのは過去の財務数値だけではありません。
事業そのものが持つ将来性や社会的価値も重要な判断材料になります。
たとえば、以下のような要素は「将来的に収益を生み出す力」として高く評価されます。
- 独自の技術力やノウハウ
- 長年培ったブランド価値
- 安定した顧客基盤やリピーターの存在
- 地域社会における雇用の維持や貢献
これらの無形資産は、現状の債務超過を乗り越え、再生後の成長を支える源泉となります。
たとえ現在は債務超過であっても、
- 事業が持つ競争力
- 社会的に存続させる意義
- 将来的に利益を生み出す可能性
が明確に示されれば、金融機関も「この会社を存続させた方が合理的だ」と判断しやすくなります。
結果として、債務免除や再生支援に前向きな姿勢を引き出せる可能性が高まるのです。
経営者に求められるのは、下記です。
- 財務改善策だけでなく、事業の強みや無形資産を言語化して伝えること
- 金融機関が納得できる形で、将来の収益可能性を示す事業計画を提示すること
金融機関に「未来への伸びしろ」を理解してもらうことこそ、債務超過からの事業承継・再生を成功させる鍵となります。
債務超過企業が事業承継を実現するための3つのポイント
債務超過の企業が「債務免除」を活用して事業承継を実現させることは容易ではありません。
そのためには、いくつかの重要な仕組みを正しく理解し、慎重に実行していくことが求められます。
特に押さえるべき要素は次の3つです。
- 第二会社方式で優良事業を切り出す
- 旧会社を特別清算して債務を整理する
- 繰越欠損金で債務免除益の税金を回避する
これら3つのポイントを押さえることで、
- 債務超過であっても廃業せずに事業承継を実現できる
- 金融機関との交渉も合理的なスキームに基づいて進められる
- 承継後の事業運営をスムーズにスタートできる
といったメリットを得られる可能性が生まれます。
詳しい内容をみていきましょう。
ポイント1:第二会社方式で優良事業を切り出す
事業再生の有効な手法のひとつに、「第二会社方式」と呼ばれるスキームがあります。
これは、債務超過にある企業が事業承継を進める際にも多く活用される方法です。
具体的には、会社の事業を以下のように分けます。
- 優良事業…将来性があり収益を生む事業
- 不採算事業・過大債務…継続すると赤字や負債の増加につながる部分
このうち、優良事業だけを新設会社(第二会社)やスポンサー企業へ事業譲渡などの形で移転させます。
第二会社方式を活用するメリット
- 後継者は、債務を切り離したクリーンな状態で事業を引き継げる
- 金融機関も、再生を前提とした債務免除に応じやすくなる
- 会社にとっても、将来性のある事業を存続できるため雇用や取引先との関係を維持しやすい
第二会社方式は、債務超過や多額の借入金に悩む企業であっても、優良事業を守りつつ事業承継を実現できる方法です。
ただし、この手法を実行するには、法務・税務・金融機関との調整など高度な専門知識が必要となるため、早い段階で専門家に相談することが成功のカギとなります。
ポイント2:旧会社を特別清算し債務を整理する
第二会社方式などで優良事業を切り出した後、旧会社にはどうしても不採算事業や過大な債務が残ります。
この旧会社を整理する有効な手法が、「特別清算」です。
特別清算は、会社法に基づく法的な清算手続きの一つで、債権者の協力のもとで柔軟に進められる点が特徴です。
破産手続きと異なり、
- 債権者との合意形成を前提に進められる
- 企業や経営者の信用毀損リスクを比較的抑えられる
- 柔軟な条件調整が可能
といったメリットがあります。
特別清算の過程で、金融機関から債務免除の同意を得られれば、旧会社に残った債務を整理できる可能性が高まります。
これにより、優良事業を引き継いだ新会社は「債務の重荷から解放された状態」で事業を継続でき、事業承継をスムーズに進めることができます。
特別清算は、
- 不採算事業と過大債務を抱えた旧会社を整理する方法
- 金融機関との協力を前提とした柔軟な清算手続き
- 債務免除を実現し、事業承継を成功させるための重要なステップ
として活用される有効な再生スキームです。
ポイント3:繰越欠損金で債務免除益の税金を回避する
事業承継において債務免除を受ける際、忘れてはならないのが税務上の取り扱いです。
債務免除を受けた場合、その金額は会計上「債務免除益」として利益計上されます。
その結果、巨額の法人税が発生し、せっかく債務整理をしても新たな資金負担を抱えてしまう危険性があります。
しかし、多くの債務超過企業は、過去の赤字による「繰越欠損金」を保有しています。
この繰越欠損金と債務免除益を相殺することで、実質的に課税を回避できる場合があります。
つまり、適切に繰越欠損金を活用すれば、債務免除を受けても法人税の負担を最小限に抑え、承継後の財務基盤を守ることが可能になるのです。
債務免除を含む事業再生スキームでは、下記が欠かせません。
- 法務・金融の調整だけでなく、税務処理を含めた総合的な設計
- 専門家によるシミュレーションと計画的な実行
税務上の落とし穴を回避できるかどうかが、事業承継スキーム全体の成否を分けるといっても過言ではありません。
第二会社方式や特別清算をはじめとする事業再生スキームは、法務・税務・金融機関との調整を要する高度な手続きです。
そのため、専門家なしでスムーズに進めるのは極めて困難です。
「自社の場合、具体的にどう進められるのか?」
「どの再生スキームを選べば最も負担が少ないのか?」
といった疑問や不安をお持ちの経営者様は、ぜひ再生型M&Aに実績豊富なジーケーパートナーズにご相談ください。
当社は、
- 第二会社方式や特別清算を組み合わせた再生スキームの設計
- 金融機関との交渉サポートと債務免除の実現
- 税務面も含めた最適な事業承継プランの提案
を通じて、貴社にとって最適な解決策を立案から実行までワンストップで支援します。
事業承継における経営者保証の整理
事業承継を進める際は、会社の債務だけでなく、経営者個人の保証債務も同時に解決することが重要です。
債務超過の企業では、経営者自身が金融機関へ個人保証をしているケースが多く、これを放置すると承継後も経営者に重い負担が残る可能性があります。
そのため、事業承継や再生を進める際には、「会社の債務」と「経営者の保証債務」を一体で整理することが原則です。
会社と経営者の債務整理に使える主な制度
①経営者保証ガイドライン(経営者個人の保証整理)
経営者が過大な個人保証を抱えている場合に、生活の再建を支援するためのルールです。
金融機関との交渉を通じて、生活に必要な資金や自宅(華美でないもの)を残せる可能性があります。
このガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会が策定した自主的ルールで、経営者の破産を回避し、再挑戦を促すことを目的としています。
②私的整理ガイドライン・中小企業活性化協議会(会社の債務整理)
会社の再生を支援する枠組みで、金融機関と協議しながら債務免除や再生計画の実行を進める仕組みです。
このスキームでは、会社の債務整理と同時に、経営者保証ガイドラインの考え方に沿って個人保証の整理も進められます。
原則として経営者の保証債務も整理の対象になる
会社の債務免除を金融機関と交渉する際には、経営者個人の保証債務も同時に整理の対象とするのが原則です。
なぜなら、会社の債務だけを整理しても、経営者に多額の保証債務が残れば、
- 経営者本人の生活が成り立たない
- 再起の意欲や余力が奪われる
- 結果的に事業再生そのものが頓挫する
といった事態に陥る可能性が高いからです。
金融機関にとっても、経営者が過大な負担を抱えたままでは再生計画の実行が不安定になるため、保証債務を含めた包括的な調整を行う方が合理的です。
債務免除を活用した事業承継の注意点
債務免除を組み込んだ事業承継は、債務超過の企業が廃業を回避し、事業を未来へつなぐための有効な手法の一つです。
ただし、その実行には高度な専門知識と慎重な手続きが求められるため、容易ではありません。
法務・税務・金融機関との調整など、複雑な要素が絡むことを踏まえて、あらかじめ注意点を理解しておくことが大切です。
事前にリスクや課題を把握し、適切な対策を講じることで、実現の難易度が高い中でも、事業承継を成功に導ける可能性を高めることができます。
後継者や従業員への丁寧な説明と合意が求められる
債務免除を伴う事業承継は、法務・財務の手続きだけでなく、後継者・従業員・取引先などステークホルダーの心情への配慮が不可欠です。
なぜこの手続きが必要なのか、会社と雇用・取引にどんな影響があるのかを丁寧に説明し合意を得ることで、不信感や噂の拡散を防ぎ、承継後の事業継続性を高められます。
逆に、たとえスキームが形式上成功しても、関係者の不信感が残ればオペレーションが崩れ、業績悪化を招くリスクがあります。
許認可の再取得や取引契約の再締結が必要になる
第二会社方式を用いて事業譲渡を行う場合、単に優良事業を切り出すだけではなく、許認可や契約関係の引き継ぎに関する実務上の対応も必要になります。
旧会社が保有していた各種許認可(例:建設業許可、古物商許可、宅建業免許など)は、原則として新会社ではそのまま使えません。
そのため、新会社で改めて再取得の申請手続きを行う必要があります。
- 業種によっては審査に数週間から数か月を要することもある
- 許認可がないと営業ができない業種では、承継直後に事業が止まってしまうリスクがある
主要な取引先との基本取引契約・代理店契約・販売契約なども、旧会社から新会社へ自動的に承継されるわけではありません。
原則として、新会社との間で契約を締結し直す必要があります。
そのため、
- 取引継続への不安から先方が再検討する可能性
- 交渉や契約更新の手間と時間
といった課題が生じる場合があります。
許認可や契約関係の問題を軽視すると、事業の空白期間(営業停止期間)が発生するリスクがあります。
これを防ぐためには、
- 承継対象事業に必要な許認可の洗い出しと再取得スケジュールの事前策定
- 主要取引先との事前説明と契約再締結の準備
- 必要に応じて承継前から新会社設立を並行して進める体制づくり
といった事前の確認と準備が不可欠です。
専門家選びで成否がわかれる
債務免除を組み込んだ事業承継は、極めて専門性の高い分野です。
金融機関との交渉力、再生スキームの設計力、M&Aの実績といった幅広い知見を持つ専門家を選べるかどうかが、プロジェクト全体の成否を大きく左右します。
実績や経験が不十分な専門家に依頼してしまうと、下記のようなリスクが現実化する恐れがあります。
- 金融機関との交渉が難航して、債務免除が得られない
- 税務処理の見落としによって、債務免除益への課税問題が発生する
- スキーム設計の不備により、承継後の経営に支障が出る
専門家を選ぶ際のチェックポイントとして、
- 類似案件の実績があるか
- 金融機関との交渉事例を持っているか
- M&Aを絡めた事業再生スキームに精通しているか
- 初回の無料相談を通じて信頼できる相手かどうかを見極める
これらを確認することで、安心して任せられる専門家かどうかを判断できます。
まとめ
金融機関の同意のもとで債務免除を受けられれば、債務超過の企業でも事業承継を実現できる可能性があります。
ただし、これは実行の難易度が高い手続きであり、慎重な準備と専門的な支援が欠かせません。
実務では、次の「3ステップ」を順序立てて進めるのが一般的です。
- 第二会社方式:優良事業を新会社(またはスポンサー企業)へ切り出し、クリーンな財務で承継開始
- 特別清算:旧会社に残る不採算事業・過大債務を、債権者の協力のもと法的手続で整理
- 繰越欠損金の活用:発生する債務免除益と相殺し、法人税負担を最小化(適用要件・上限に留意)
ポイントは、私的整理ガイドラインなどの公的枠組みを活用し、金融機関が納得できる合理的な回収シナリオを提示できるかどうかが、成功の分かれ目となります。
実行を成功させるための要点は、下記のようなものがあります。
- 計画の整合性:財務・法務・税務・労務・許認可を一体で設計
- ステークホルダー対応:従業員・主要取引先・金融機関への説明と合意形成を段階設計
- 許認可・契約の事前手当:再取得や契約再締結のタイムラグで“空白期間”を作らない
- 税務の検証:繰越欠損金の適用可否・上限、グループ内取引の時価性等を事前にチェック
これらの手続きは高度に専門的で、設計・交渉・実行のすべてに熟達が必要です。
経験不足のまま進めると、
- 金融機関交渉の難航
- スキーム不備による税務リスク顕在化
- 許認可・契約対応漏れによる営業停止
といった重大なリスクにつながります。
「借入金が重く、債務超過だから事業承継は不可能だ」と思い込んでいませんか?
しかし、再生スキームを活用すれば、債務超過の状態でも事業承継を実現できる可能性があります。
債務免除を絡めた事業承継は、「金融機関との交渉経験」「再生スキームの設計ノウハウ」「M&A・事業再生の実績」が求められる高度な分野です。
誤った進め方をすると、承継が頓挫したり、余計な税務負担が発生したりするリスクもあります。
- 中小企業活性化協議会の外部専門家として数多くの再生案件に関与
- 債務超過案件に強い再生型M&A支援の実績多数
- 法務・財務・税務・金融交渉を一体でサポート
といった経験を活かし、貴社の状況に合わせた最適な解決策をご提案します。
事業承継を前に「何から始めればよいのか分からない」とお悩みなら、まずはお気軽にご相談ください。
無料個別相談会では、貴社の現状を丁寧にお伺いし、具体的な一歩を一緒に考えます。
貴社の状況に合わせた最適な解決策をご提案します。