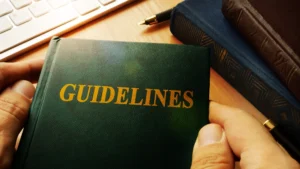
中小企業の経営者にとって「事業を誰に、どのように引き継ぐか」は避けて通れない大きな課題です。
特に、債務超過や借入金の問題を抱えていると、「本当に承継なんてできるのか?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな中、国が策定した「事業承継ガイドライン(最新版:2022年改訂)」が注目を集めています。
このガイドラインは、後継者不在や承継プロセスの複雑さといった課題に対し、実践的な指針を示すものです。
本記事では、事業承継ガイドラインの基本から具体的な活用法までを解説します。
特に「財務的な課題を抱える中小企業が、どのように承継を実現できるのか」という視点から、専門家の視点でわかりやすく紹介します。
借入金や債務超過の不安から、事業承継やM&Aをあきらめていませんか?
ジーケーパートナーズでは、債務超過・財務課題を抱える企業の再生型M&Aや私的整理に多数の実績があります。
一般的な仲介会社では対応できない複雑な案件も、私たちなら支援可能です。
まずは無料個別相談で、解決の道筋を一緒に見つけませんか?
事業承継ガイドラインとは何か
中小企業の経営者にとって、事業承継は「後継者の不在」や「債務の引き継ぎ」など、複雑な問題が絡む難しいテーマです。
こうした課題に対応するため、中小企業庁は「事業承継ガイドライン」を策定し、事業承継の進め方をステップごとに示しています。
このガイドラインは、再生型M&Aや私的整理と組み合わせた承継を検討する経営者にも、有益な手引きとなります。
事業承継ガイドライン策定の背景と目的
日本企業の99.7%を占める中小企業では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な課題となっています。
中でも、資金繰りや債務問題を抱えた企業では、円滑な事業承継が難しく、「廃業」という選択を迫られるケースも少なくありません。
このような状況に対応するため、中小企業庁は2006年に「事業承継ガイドライン」を策定しました。
その後、2016年および2022年に改訂を行い、時代の変化に即した承継の在り方を示してきました。
現在、このガイドラインは、後継者不在や財務課題を抱える経営者にとって、有効な対策指針となっています。
ガイドラインの3つの柱
「事業承継ガイドライン」は、以下の3つの柱に基づいて構成されています。
これにより、経営者は事業承継を体系的かつ段階的に進められるようになります。
- 早期の取り組みの重要性
→経営者が自身の事業の承継リスクを把握するため、「事業承継診断」などを通じた現状分析を促します。
- 事業承継に向けて踏むべき5つのステップ
→後継者の選定、経営の見える化、株式・資産の整理など、段階ごとの準備内容が示されています。
- 地域における支援体制の強化
→中小企業活性化協議会や金融機関、士業など地域の支援機関と連携して、円滑な承継を支える体制の整備が求められています。
事業承継に向けた5つのステップ
「誰に、いつ、どうやって事業を託すのか」、これは事業承継における最大の悩みです。
事業承継ガイドラインでは、経営者がこの問いに段階的に向き合えるよう、5つのステップを示しています。
このステップに沿って取り組むことで、後継者の選定・関係者との調整・資産や株式の整理など、複雑な承継プロセスを体系的に進めることが可能になります。
ステップ1:事業承継の必要性への理解
事業承継を成功させる第一歩は、経営者自身がその重要性に気づくことです。
「まだ元気だから大丈夫」と考えて準備を先送りにする経営者は少なくありませんが、後継者探しや承継の準備には想像以上に時間がかかります。
中小企業庁では、60歳を迎えたら承継準備に着手し、60歳を過ぎている場合はすぐに支援機関に相談を始めることを推奨しています。
これは、後継者の選定や社内外の関係者調整、資産・株式の整理など、実際の承継プロセスに数年かかるケースが多いためです。
また、事業承継は単なる経営権の引き継ぎではなく、企業の持続的な発展と従業員の雇用維持を図るための“戦略”でもあります。
だからこそ、役員や従業員、取引先などの関係者に事業承継の方針と意義を丁寧に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。
ステップ2:経営状況・課題の可視化
事業承継を成功に導くには、まず自社の現状を客観的に把握することが不可欠です。
経営者自身が「自社の強みと弱み」「どこに課題があるのか」を整理することで、後継者も安心して経営を引き継ぐことができます。
特に以下の4つの視点からの分析が重要です。
①事業面の分析
- 競合他社との比較(シェア・価格・技術力など)
- 自社商品の強みと弱み
②財務・資産面の分析
- 貸借対照表や資金繰りの確認
- 個人資産と法人資産の切り分け(混同があると承継時に問題に)
③組織と人材の把握
- キーパーソンの存在と将来性
- 組織体制の継続性
④市場環境と競争力
- 業界全体の成長性・課題
- 自社の立ち位置と今後の展望
こうした分析によって、事業承継に向けた優先課題が明確化されると同時に、経営改善のヒントも得られます。
後継者にとっても、「どこを伸ばし、どこを立て直せばよいか」を理解するための大切な土台となります。
ステップ3:事業承継に向けた経営改善
現状分析によって明らかになった課題をもとに、事業承継前の経営改善に取り組むことが重要です。
引き継ぎをスムーズにするには、「後継者が引き継ぎたくなる会社」に整えておく必要があります。
具体的には、以下の4つの観点から改善を進めます。
①事業ポートフォリオの見直し
- 不採算事業の整理・撤退
- 収益性のある主力事業への集中
- 成長分野での新規事業の検討
②財務体質の健全化
- 資金繰りの見直しと最適な資金調達
- 借入条件の再交渉
- 財務指標(自己資本比率・キャッシュフロー等)の改善
③組織体制と人材育成
- キーパーソン育成と属人化の解消
- 組織図と責任範囲の明確化
- 社員の自立性を高める人材戦略
④業務の見える化・標準化
- 手順マニュアルやルール整備
- 業務プロセスの共有化とIT活用
- 後継者が引き継ぎやすい運営体制づくり
これらの改善により、企業価値そのものが高まり、後継者が“未来を託されたい”と感じる状態を目指すことができます。
ステップ4:事業承継計画の立案・策定
経営改善の成果を踏まえて、具体的な事業承継計画を策定するフェーズに入ります。
計画は、後継者が安心してバトンを受け取れるよう、資産や経営の移転方法、時期、関係者の役割分担を明確に整理しておくことが重要です。
承継方法に応じて、検討すべきポイントは異なります。
【親族内・従業員への承継の場合】
- 後継者の選定と育成計画
→実務引継ぎ、理念の共有、社内外の信頼構築がポイント
- 株式・資産承継の手法
→相続・贈与・譲渡の比較検討、議決権の整理など
- 税務・法務対策
→相続税対策、遺留分、株価評価など専門的観点も必要
【第三者承継(M&A)の場合】
- 企業価値の最大化
→財務体質の改善、事業ポートフォリオの見直し
- 譲渡スキームの選定
→株式譲渡か事業譲渡か、債務超過であれば再生型M&Aも視野に
- 適切な相手先の選定と交渉支援
→従業員の雇用や理念継承を重視する買い手かどうかも重要
【計画実行に向けたポイント】
- スケジュールとマイルストーンの設定
- 後継者教育プログラムの策定
- 関係者との継続的な情報共有
→承継を巡って社内で温度差が生まれやすいため、丁寧な合意形成が不可欠
こうした要素を組み合わせて計画的に準備を進めることで、承継に伴うトラブルや混乱を未然に防ぎ、組織全体が一体となって未来に進める体制が整います。
ステップ5:事業承継およびM&Aの実行
策定した事業承継計画に基づき、いよいよ実行フェーズに入ります。
この段階では、法務・税務・社内外の調整といった多面的な対応が必要となり、抜け漏れなく進めるためには専門家との連携が欠かせません。
主な実行項目は以下の通りです。
- 法的手続きと契約の整備
→株式譲渡契約、経営委任契約、役員変更登記など
- 税務対策と優遇措置の活用
→事業承継税制、贈与税・相続税の納税猶予などの制度利用
- 関係者への丁寧な説明と理解促進
→従業員・取引先・金融機関など、安心感と信頼継続のための対応
- 新体制の立ち上げと支援
→後継者による経営体制の確立と、前経営者・支援者による伴走的サポート
実行段階では、計画どおりに進まないこともあります。
思わぬ相続人の主張、株式の評価のズレ、従業員の不安など、現場ではさまざまな課題が生じがちです。
だからこそ、弁護士・税理士・承継支援の専門家と連携しながら、柔軟に対応していく体制が成功のカギとなります。
複雑な事業承継やM&Aの実行には、高度な専門知識と豊富な現場経験が不可欠です。
ジーケーパートナーズでは、中小企業活性化協議会の外部専門家として数多くの企業支援に携わってきた実績をもとに、財務・事業デューデリジェンスから計画策定、実行支援まで、一気通貫でサポートいたします。
特に、債務超過企業や借入負担の大きい企業における再生型M&Aや私的整理スキームなど、他の仲介会社では対応が難しいケースにも柔軟に対応できる点が、当社の強みです。
「承継したくても、負債がネックで動けない」
「M&Aを検討したいが、どこに相談すればいいか分からない」
そんなお悩みをお持ちの方は、まずは無料の個別相談会をご利用ください。
今の状況を整理するだけでも、次の一手が見えてくるかもしれません。
関連記事|事業承継M&Aとは?メリット・デメリットから成功のポイントまで徹底解説
事業承継支援体制の活用方法
事業承継ガイドラインでは、地域における支援体制の重要性も強く打ち出されています。
なぜなら、事業承継は法律・税務・財務・人事など多岐にわたる知識が必要なうえ、感情面や組織内調整といった繊細な配慮も求められる、極めて専門的なプロセスだからです。
実際、多くの中小企業経営者が「後継者は決まっているが、何から始めればいいか分からない」「専門家に相談するタイミングが分からない」といった悩みを抱えています。
だからこそ、親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)のいずれであっても、商工会議所・中小企業活性化協議会・認定支援機関・士業(税理士、弁護士など)といった専門機関やプロフェッショナルと連携することが不可欠です。
支援機関は、承継の初期段階から計画策定、実行、フォローアップに至るまで、状況に応じたアドバイスと具体的支援を提供してくれます。
どのような支援機関が、どんな場面で活用できるのかを、次に詳しく解説します。
承継を進める上で、あなたの“強力な味方”となる情報です。ぜひ参考にしてください。
公的支援機関を利用する
各都道府県に設置されている公的な支援機関(例:事業承継・引継ぎ支援センター等)では、事業承継に関する無料相談を受けることができます。
親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A)など、あらゆる承継形態に対応しており、経営者の状況に応じた最適な承継方法を提案してもらえるのが大きな特徴です。
公的支援機関の主なサポート内容は下記の通りです。
- 親族内・従業員承継の場合
→後継者選定の考え方、育成プラン、税務・相続対策の基本整理など
- M&Aを検討する場合
→信頼できる仲介事業者の紹介、手続きの流れの説明、契約上の注意点など
- 共通サポート
→「事業承継診断」による課題整理、スケジュール立案、関係者調整のアドバイス
各企業には専門のコーディネーターが付き、課題の棚卸しから対応方法の提案、必要に応じた士業・支援機関とのマッチングまでを一貫して支援してくれます。
実際の相談は、電話・WEB・対面相談(予約制)などで受け付けており、「何から始めればいいかわからない」という段階でも気軽に相談可能です。
公的支援機関は中立的な立場でアドバイスを行うと同時に、民間の専門家との連携による支援体制の構築も進めています。
事業承継を本格的に進める際には、こうした支援機関と連携しながら、財務やM&Aに強い専門家(例:ジーケーパートナーズ)と組むことで、より実効性のある計画が実現できます。
専門家を活用する
事業承継では、税務・法務・財務・経営戦略など、多岐にわたる専門知識が必要とされます。
そのため、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士などの専門家と連携し、多角的な支援を受ける体制づくりが極めて重要です。
専門家の主な役割は下記の通りです。
- 税理士
→贈与・相続・譲渡にかかる税務対策、事業承継税制の活用支援
- 公認会計士・財務アドバイザー
→企業価値評価、財務デューデリジェンス、資金繰りの見直し
- 弁護士
→契約書作成、株式・資産承継に関わる法的整備、係争リスク対応
- 中小企業診断士
→経営状況分析、承継計画策定、後継者育成支援
特にM&Aを含む第三者承継の場合は、買収側との交渉・法的手続き・税務面での最適化など、より高度で実務的な対応が求められるため、専門家の伴走支援は不可欠です。
全国にある事業承継・引継ぎ支援センターでは、これらの専門家と連携した実践的なサポート体制を整えています。
企業の状況に応じて、適切な士業やアドバイザーを無料で紹介してもらえるほか、M&A仲介事業者とのマッチング支援も可能です。
また、2025年度の事業承継・M&A補助金では、
- 専門家の活用にかかる費用(例:デューデリジェンス費用、契約支援、税務アドバイス)
- 仲介費用や事業引継ぎに伴う経費
などが補助対象となる可能性があり、活用すれば実質的な負担を大幅に軽減できます。
金融機関と連携する
地域の金融機関も、近年は事業承継支援に積極的に取り組んでおり、中小企業にとって大きな支援先の一つとなっています。
特に、計画段階から実行・資金調達まで一貫して寄り添ってくれるパートナーとして活用が可能です。
金融機関の主な支援内容は下記の通りです。
【情報提供・専門部署による伴走支援】
- 多くの地域金融機関には事業承継・M&A専門部署が設置されており、経営者の状況に応じた提案が可能
- 専門部署がM&A仲介業者とのネットワークを活用し、信頼できる支援先の紹介も実施
【資金面での支援】
- 買収資金の融資や、売却代金の運用アドバイスなど、M&Aにおける金融支援を提供
- 事業承継ファンド・M&A専門ファンドと連携することで、第三者承継時の資金確保にも対応可能
【継続的な関与・アドバイス】
- 取引金融機関は、顧客企業の財務状況や信用力を熟知しているため、承継計画の妥当性やリスクなどについて、現実的で踏み込んだアドバイスが可能
- 計画の初期段階から資金スキーム構築、実行後の経営支援まで、中長期的な支援が期待できる
特に、債務超過や資金繰りに課題を抱える企業にとっては、金融機関との関係性は事業承継成功の鍵を握る重要な要素です。
早めに信頼できる担当者と面談し、“承継を前提とした資金設計”を始めることが、次の一歩につながります。
関連記事|債務超過と銀行の関係は?融資への影響と対応策をご紹介
まとめ
「事業承継ガイドライン」は、親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)といったさまざまな形態に対応できる、中小企業のための実践的な指針です。
経営者が60歳になったら準備を始めるべきという考え方は、単なる推奨ではなく、事業の持続可能性を左右する重要な判断です。
ガイドラインで示された5つのステップを体系的に実践することで、どの承継パターンでも成功の確率を大きく高めることができます。
2025年現在、経営者の高齢化はますます深刻になっており、事業承継は“待ったなし”の経営課題です。
これまで見てきたように、支援機関・専門家・金融機関といった体制を活用することで、承継は決して一人で抱えるものではありません。
まずは一歩踏み出すことが、成功への第一歩です。
本記事で紹介した支援体制を積極的に活用し、まずは信頼できる支援機関への相談から始めてください。
それが、自社にとって最適な承継方法を見つける第一歩となります。
ジーケーパートナーズは、企業再生コンサルティングの豊富な経験を活かし、債務超過企業の再生スキームを絡めたM&Aや、私的整理ガイドラインを用いた事業譲渡・会社分割など、一般的なM&A仲介では対応が難しい複雑なケースにも対応可能です。
中小企業活性化協議会の外部専門家として培った実践的なノウハウとネットワークを活かし、貴社の事業承継・再生を実行フェーズまで一気通貫でサポートいたします。
「負債があるけれど承継できるのか?」「後継者がいないけれど会社を残したい」
そんなお悩みをお持ちの方も、まずはお気軽に無料個別相談会をご利用ください。
現状を整理するだけでも、“次の一手”がきっと見えてきます。




