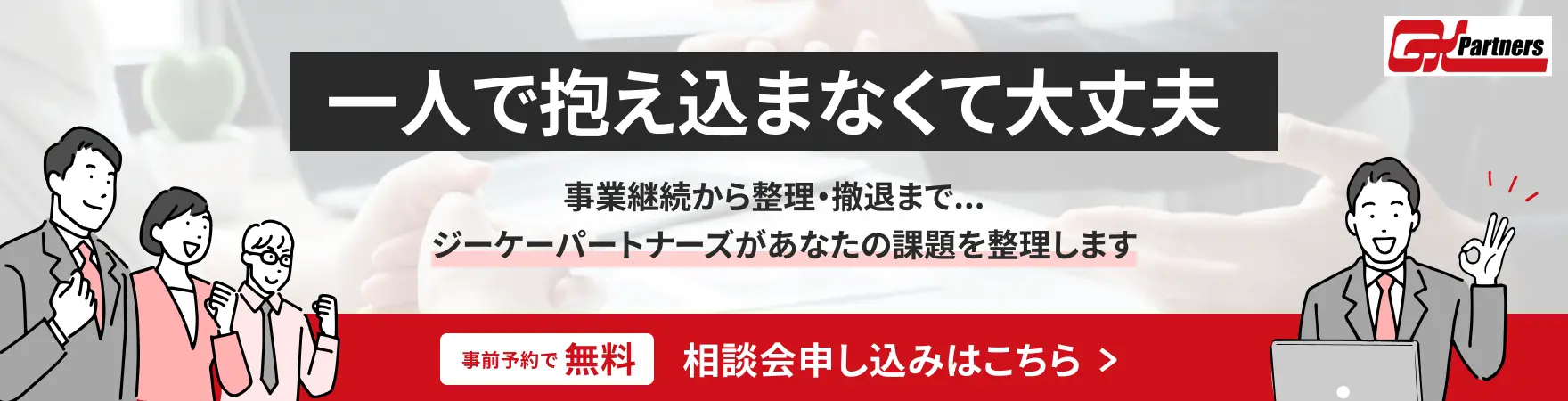会社の純資産がマイナスになっていたら、債務超過の状態です。
「債務超過って具体的にどういう状態?」「赤字とは違うの?」と疑問に感じている方もいるでしょう。
債務超過とは会社の資産よりも負債が多い状態を指すため、放置するのは危険です。
この記事では、債務超過と純資産の基本的な関係から、貸借対照表での見方、赤字との明確な違いを詳しく解説します。
また、原因やリスク、対処法についても解説しますので、健全な経営を取り戻す一歩としてご一読ください。
借入金が多すぎて会社を手放したいとお考えではありませんか?
ジーケーパートナーズでは負債整理から事業再生まで企業の状況に合わせた解決策をご提案します。
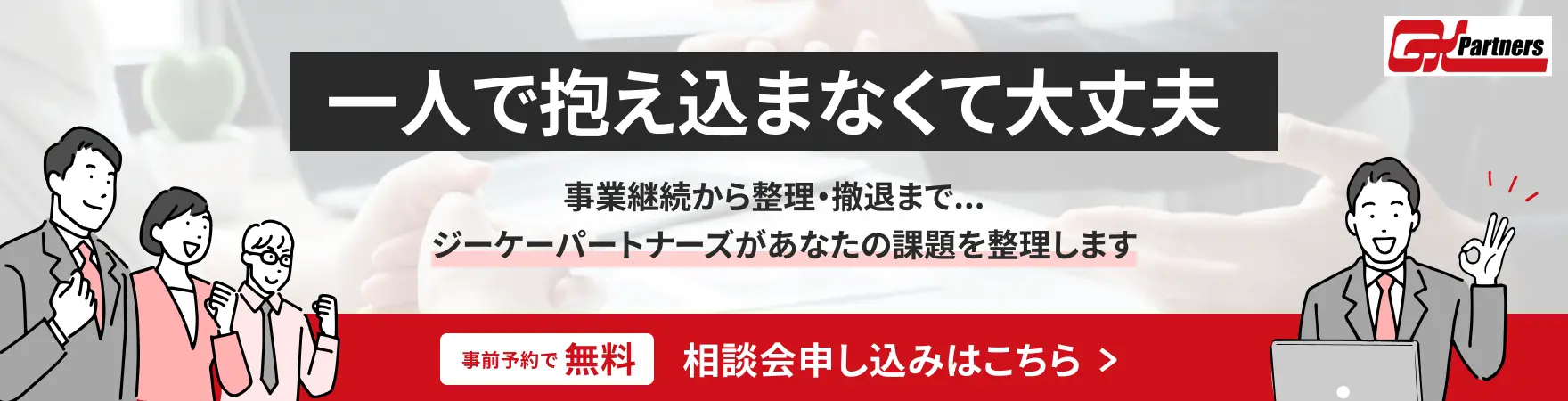
債務超過とは?純資産マイナスの状態
債務超過とは、会社の負債額が資産総額を上回っている状態を指します。
つまり、会社が持つすべての資産を売却しても、抱えている借入金などの負債を返しきれない状況です。
この状態は、会社の財務状況を示す重要な書類である「貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)」、通称バランスシート(B/S)で確認できます。
貸借対照表の右下にある「純資産の部」の合計額がマイナス(例:△1,000万円)となっていれば、その会社は債務超過に陥っている状態です。
純資産は、会社が実質的に保有している価値を示す重要な指標であり、債務超過は会社の存続に関わる非常に深刻なサインといえます。
そもそも純資産とは?
純資産とは、会社の総資産から総負債を差し引いた残りの部分を指します。
「自己資本」とも呼ばれ、返済する必要のない、会社自身が実質的に所有している財産です。純資産は、主に以下の要素で構成されます。
| 項目 | 内容 |
| 資本金 | 株主が出資したお金のうち、会社法で資本金と定められた額 |
| 資本剰余金 | 出資金のうち資本金としなかった部分(資本準備金)や、自己株式の処分差益など |
| 利益剰余金 | 会社が設立されてから生み出してきた利益の蓄積(内部留保) |
純資産が多いほど、会社の財務基盤は安定しているといえます。特に利益剰余金が厚い会社は、経営が順調である証拠です。
関連記事|債務超過時のバランスシートの例をご紹介!確認方法や解消する方法とは
債務超過と赤字の決定的な違い
債務超過と赤字は、どちらも会社の経営状態が良くないことを示す言葉ですが、その意味は根本的に異なります。
赤字は一定期間の「収支」の問題であり、債務超過はある時点での貸借対照表を基準とした「資産と負債」の残高の状態(バランス)の問題です。
この違いを理解しないと、会社の本当の財務状況を見誤る可能性があります。それぞれの意味を正しく把握しましょう。
具体的には、赤字が「フロー」、債務超過が「ストック」という点で異なります。
以下で詳しい内容をみていきましょう。
赤字は収益<費用(フロー)
赤字とは、一定期間における会社の「収益」よりも「費用」のほうが多い状態を指します。
これは、会社の経営成績を示す「損益計算書(そんえきけいさんしょ)」(P/L)で確認することができます。
たとえば、1年間の売上よりも、仕入れや人件費、家賃などの経費の合計額が大きければ、その期は赤字決算となります。
赤字は、特定の期間(通常は1年間)における会社の活動の流れ(フロー)を示す指標です。
その期間にお金がどれだけ入ってきて、どれだけ出ていったか、その結果としての損益を表します。
一時的な赤字であればすぐに問題とはなりませんが、赤字が継続すると、会社内部に蓄積された利益(利益剰余金)が減少し、やがて債務超過に陥る原因となります。
債務超過は負債>資産(ストック)
債務超過とは、ある特定の時点において、会社の「負債」の総額が「資産」の総額を上回っている状態です。
これは会社の財政状態を示す「貸借対照表」(B/S)で確認でき、純資産がマイナスになっている状態だといえます。
つまり、会社が今すぐ活動をやめて全資産を売却しても、借金などの負債を返しきれない状況を示すものです。
債務超過は、ある一時点での会社の資産状況(ストック)を示す指標です。
継続的な赤字によって利益剰余金がマイナスとなり、結果として債務超過に陥るケースが多いですが、「赤字=債務超過」ではありません。
関連記事|債務超過と赤字の違いを図解で徹底解説!判断基準・実例・解消法5選
債務超過を招く3つの主な原因
債務超過という深刻な状態に陥る原因はさまざまですが、特に多く見られる主な原因が3つあります。
- 継続的な赤字による純資産減少
- 過大な投資による負債増加(投資の失敗)
- 資産価値の下落や評価損発生
以下で詳しい内容を解説します。
1. 継続的な赤字による純資産減少
債務超過に陥る最も典型的な要因は、継続的な赤字経営です。
事業で赤字が続くと、まずは会社が過去に蓄積してきた利益剰余金が取り崩されていきます。
さらに赤字が拡大すれば、利益剰余金がマイナスに転じ、資本金や資本剰余金といった出資者からの元手部分を上回る損失を抱えることになります。
その結果、貸借対照表上の純資産全体がマイナスとなり、債務超過の状態に陥るのです。
赤字が慢性化する背景には、売上の低迷や固定費の重さ、採算の合わない事業構造などがあります。いずれにしても、早期の収支改善が求められます。
2. 過大な投資による負債増加(投資の失敗)
将来の成長や収益拡大を見込んで行った投資が期待通りの成果を上げられなかった場合、それが債務超過に至る原因となることがあります。
たとえば、新規事業への進出や大規模な設備投資などでは、自己資金や借入金を用いて多額の資金が投じられます。
こうした投資が収益につながらなければ、取得した資産の価値は目減りし、減損処理や費用計上によって純資産が圧迫されます。
特に借入金を用いた場合には、投資の失敗に加えて利息などの資金コストも継続的に発生し、財務状態を一層悪化させる要因となります。
収益化の見通しが甘かったり、判断のタイミングを誤った場合には、負債の有無にかかわらず、債務超過に陥るリスクが高まるのです。
3. 資産価値の下落や評価損発生
保有している資産の価値が、購入時や帳簿上の価格よりも大幅に下落した場合も、債務超過の原因となりえます。
会社が保有する資産には、現金や預金だけでなく、土地や建物といった不動産、機械設備や株式などの有価証券、売掛金(取引先からの未回収代金)などが含まれます。
これらの資産の市場価値が、経済状況の変化や経営環境の悪化などによって大きく下がることがあります。
たとえば、地価の暴落で不動産の価値が半減したり、投資先の株価が急落したりする場合です。
また、取引先の倒産で売掛金が回収不能になる場合も実質的な資産価値の下落といえます。
このような場合、決算時に資産の評価損を計上する必要が生じ、その損失額が大きければ純資産を一気に減らし、債務超過を引き起こす引き金となります。
放置は危険!債務超過の4大リスク
純資産がマイナスである債務超過の状態は、会社にとって非常に危険な信号です。
特に注意すべきリスクは大きく分けて以下の4つがあります。
- 金融機関からの融資停止リスク
- 取引先からの信用低下リスク
- 上場企業は上場廃止のリスク
- 最悪の場合、倒産に至るリスク
以下で詳しい内容をみていきましょう。
1. 金融機関からの融資停止リスク
債務超過の会社は、金融機関からの信用を大きく損なっており、新たな融資を受けるのが非常に困難になります。
金融機関は融資を判断する際、企業の返済能力を厳しく審査しますが、その重要な指標のひとつが貸借対照表の純資産です。
純資産がマイナスとなっている債務超過の状態は、返済能力に大きな懸念があると見なされがちです。
このため、運転資金や設備資金の調達を目的とした融資申請は通りづらくなり、資金調達の選択肢が狭まります。
必要な資金を確保できなければ、資金繰りが悪化し、事業の維持や成長にも深刻な影響が生じかねません。
2. 取引先からの信用低下リスク
債務超過であるという事実は、仕入先や販売先といった取引先からの信用低下にもつながります。
会社の財務状況は、決算公告や信用調査会社のレポートなどを通じて、外部に知られる可能性があります。
新規取引を開始する際には、相手企業が財務状況をチェックするのが通常です。
もし債務超過であることが知られれば、取引先は「この会社は代金をきちんと支払えるだろうか」「安定的に商品やサービスを供給できるだろうか」といった不安を抱きます。
その結果、現金での支払いを求められたり、掛け取引(後払い)の限度額を下げられたりするなど、取引条件が悪化する恐れがあるでしょう。
最悪の場合、取引そのものを停止されてしまう可能性も否定できません。
3. 上場企業は上場廃止のリスク
株式市場に上場している企業にとって、債務超過はさらに深刻な意味を持ちます。
各証券取引所は、上場企業に対して一定の財務基準を満たすよう求めており、その基準の一つに「債務超過の状態でない」が含まれるため注意が必要です。
もし上場企業が債務超過に陥った場合、すぐに上場廃止になるわけではありませんが、「上場廃止に係る猶予期間」に入ります。
この猶予期間内に債務超過の状態を解消できなければ、残念ながら上場廃止となるでしょう。
上場廃止となると、株式の市場での売買ができなくなり、資金調達の選択肢が大きく狭まるだけでなく、会社の社会的信用も大きく損なわれる結果となります。
4. 最悪の場合、倒産に至るリスク
債務超過の状態が改善されずに続けば、最終的には会社の倒産につながる可能性が非常に高まります。
債務超過そのものが、法律上の倒産(たとえば破産)を直接意味するわけではありません。
たとえ純資産がマイナスでも、手元に資金があり、日々の支払いが滞りなく行えていれば、事業を継続できる場合もあります。
しかし、債務超過の会社は金融機関からの融資が受けにくく、取引先との関係も悪化しがちです。
そのため、資金繰りが厳しくなっていくケースがほとんどでしょう。
債務超過を脱却する方法3選
債務超過という厳しい財務状況に陥ってしまっても、諦める必要はありません。
状況を改善し、会社を立て直すための方法は存在します。
ここで紹介する、債務超過から脱却するための代表的な方法は以下3つの通りです。
- 増資による資本金の増加
- 抜本的な収支改善で利益を増やす
- M&Aによる事業再生や売却
以下で詳しい内容を解説します。
1.増資による資本金の増加
債務超過を解消する直接的な方法の一つが、増資によって資本金を増やすやり方です。
増資とは、会社が新たに株式を発行するなどして、事業の元手となる資本金を増やす手続きを指します。
これにより貸借対照表の純資産の部が増加するため、マイナスだった純資産がプラスに転じ、債務超過を解消できる可能性があります。
出資者としては、経営者自身やその親族、関係の深い取引先、あるいは事業の将来性に期待する投資ファンドなどが考えられます。
借入れとは異なり返済義務のない自己資本を増やせるため、財務体質の強化につながる点がメリットです。
ただし、新たに出資してくれる人を見つける必要があり、特に業績が悪化している状況では容易ではありません。
また、新たな株主が増えることで、経営への関与や配当への配慮が必要になる場合もあります。
2.抜本的な収支改善で利益を増やす
債務超過の根本的な解決を目指すなら、収益力を高めて利益を増やす方法が不可欠です。
特に継続的な赤字が債務超過の原因である場合には、この取り組みが最も重要になります。
具体的な取り組みとしては、まずは固定費の見直しや業務プロセスの効率化など、不要なコストを徹底的に削減したり、抜本的には、不採算となっている事業や部門からの撤退などの改善策が考えられます。
同時に、主力商品の競争力向上、新たな収益源となる新商品・サービスの開発、効果的な販路の開拓、価格戦略の見直し、顧客満足度の向上など付加価値を向上させる改善策も重要です。
商品やサービスの付加価値を高め、適正な価格設定を行うことで、同じ売上高でもより高い利益を確保できるようになります。
時間はかかるかもしれませんが、事業の収益構造そのものを変革できれば、持続的な財務健全化につながります。
3.M&Aによる事業再生や売却
自社だけの力で増資や事業改善を進めるのが難しい場合には、M&A(企業の合併・買収)を活用するのも有効な選択肢となります。
M&Aと聞くと大企業の話と思われがちですが、近年は中小企業でも事業再生や承継の手段として活用されるケースが増えています。
例えば、より経営体力のある企業の傘下に入り、資金面や経営ノウハウ面での支援を受けながら再生を目指す方法(株式譲渡や第三者割当増資など)があります。
また、会社全体ではなく、一部の事業や含み益のある遊休資産などを切り出して他社に売却(事業譲渡や会社分割など)し、その対価で負債を圧縮して財務を改善する方法も考えられるでしょう。
M&Aは、外部の資本や経営資源を取り込むことで、自社単独では難しかった早期の債務超過解消や事業再生を実現できる可能性があります。
債務超過企業専門のM&Aプラットフォームなどを活用するのも一つの手です。
ジーケーパートナーズでは、専門家による無料相談会を実施中です。企業再生をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
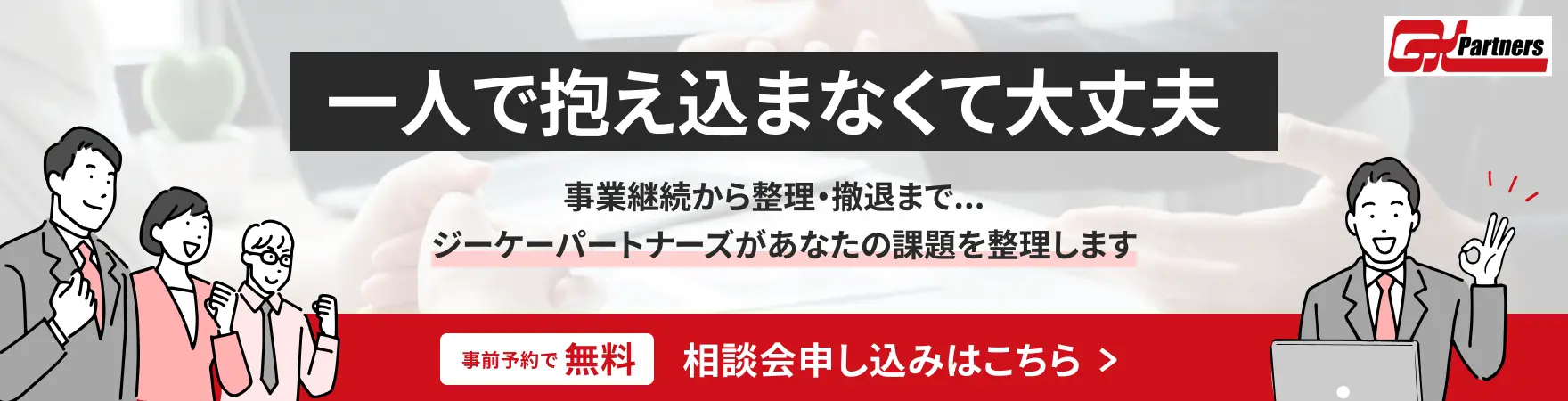
まとめ
債務超過とは、会社の負債が資産を上回っている状態を指し、貸借対照表における純資産のマイナスとして明確に示されます。
これは、会社が持つすべての資産を売却しても、借金などの負債を返しきれない状況です。
一方、赤字は損益計算書上の収益が費用を下回る状態であり、一定期間の経営成績を示すものです。
債務超過と赤字は意味合いが異なりますが、継続的な赤字は純資産を減少させ、債務超過の大きな原因となるため注意してください。
会社の財政状態を把握するためには、貸借対照表と損益計算書の両方を確認することが重要です。
どの対策が最適かは、会社の状況によって異なるため、専門家のサポートを受けながら、自社に適した方法を検討するのがおすすめです。
ジーケーパートナーズでは無料個別相談会も開催中です。専門家が直接アドバイスを行い、最適な解決策をご提案しますので、お気軽にお問い合わせください。