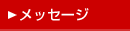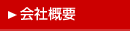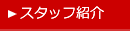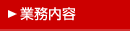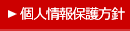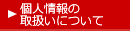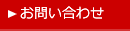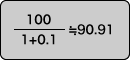| セミナー内容
1. 趣旨
商売が順調で、返済が遅れていなくても、借入が過大であれば不良債権と見なされる。そうならないための予防策と、不良債権(分類先)にされたときの対応策について
2. 銀行が不良債権の処理を急ぐ理由
| ① |
日本の金融界は、もともと護送船団方式と呼ばれ、裁量行政を旨とした。 |
| ② |
ところが、世界規模の市場経済に巻き込まれた(自由競争・グローバルスタンダード)。 |
| ③ |
具体的には、大手銀行の自己資本は8%を要求され、また、ペイオフを実施することになった。 |
| ④ |
ペイオフを実施するとなれば、預金者に対しては、銀行選択の判断基準として、銀行経営の中身を開示する必要がある(透明性を必要とされる)。 |
| ⑤ |
自己査定制度(信用リスク制度)が創設され、あくまで(役所に調べられるのではなく)、自らの手で情報を開示することが必要になった(役所による検査は、事後確認)。 |
| ⑥ |
不良債権が多ければ、その銀行はどうなるか?
⇒不良債権の処理ができなければ市場の信任を得られない
⇒預金は流出、金融市場でも資金を得られない
⇒破綻 |
※長銀や拓銀は資産超過だったと言われているが、金繰りがつかずに、破綻した。 |
3. それでも不良債権は減らない
(1)理由1:銀行の対応が厳しくなった(借入手形の書き換えをしないなど)
(2)理由2:そもそも不良債権の定義が広がっている(延滞していなくても、不良債権)
4. 自己査定の概要
債務者区分 <金融検査マニュアル>※、<債務者区分判定シート>※
※以上に関しては割愛させていただきます。
5. 不良債権の入り口
| (1) |
要注意債権~幅広く抽出される。その銀行からの借入は継続できるが、借入金利が高くなる |
| (2) |
要管理債権~要注意先に対する債権のうち、リスク管理債権に該当する貸出金のことを指し、「3ヶ月以上延滞債権」と「貸出条件緩和債権」が該当する |
6. 対策
(1)(返済のための)追加融資を受けないこと(すぐに、また苦しくなる)
(2)決済資金がどうしても必要な場合には、別の銀行で借りた方が、借りやすい
(3)全面肩代わりを考えてみる(大手銀行⇒地方銀行⇒信金・信組)
(4)他府県地銀の大阪支店が狙い目
(5)外資系銀行も活用
いずれの場合も早めの対策が必要
7. 銀行の処理方法
(1)①直接償却、②間接償却、③バルクセール
(2)バルクセール=第三者への債権売却
(3)債権の額面ではなく、時価で取引される
(4)DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー=割引現在価値)で評価する
来年の100円は、今、いくらの価値があるか?
割引率を10%とすると、
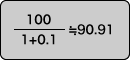
※なお、この10%は金利ではなく、利益やリスク率も勘案した数字
8. 企業再生を果たそう
(1)間違った対応1:お願いベースの交渉
(2)間違った対応2:金融機関特有のルールを知らない
9. 企業再生の条件
| (1) |
企業再生先に選ばれよう |
| (2) |
企業再生(事業再生)の条件 |
| |
①誠実な債務者であり、再生に強い意欲を有しているか |
| |
②債権者(銀行)にとって、経済合理性があるか |
| |
③当該事業に事業価値があるか |
| |
④主要債権者やその他の債権者の同調が見込まれるか |
| |
⑤経営責任・株主責任の明確化が可能か |
| |
⑥地域経済への影響はどうか |
| (3) |
債務超過や借り入れがいくらあろうとも、キャッシュフローが5千万円程度あると、周りの協力が得られやすい |
| (4) |
整理回収機構(=RCC)では、再生に法的整理も有り得るので、要注意 |
10. 企業再生の方法
| (1) |
具体的方法→銀行から、単純に免除を得るのは不可能と知る |
| |
理由①:合理的な免除額を算出することが難しい |
| |
理由②:公平性の問題 |
| (2) |
債権買取をする場合 |
| |
①自分で銀行調達する→○ |
| |
⇒ |
貸し出し銀行にとっては、貸し出す時点では不良債権。従って、ひと工夫が必要 |
| |
②投資家に債権を買ってもらう→△ |
| |
⇒ |
投資家が入ると、彼らの利益が上乗せされる |
| |
③隠していた自己資金→× |
| |
⇒ |
絶対にダメ。債権を買い取りできないだけではなく、差押さえされることも |
11. 整理回収機構の概要
以上。 |